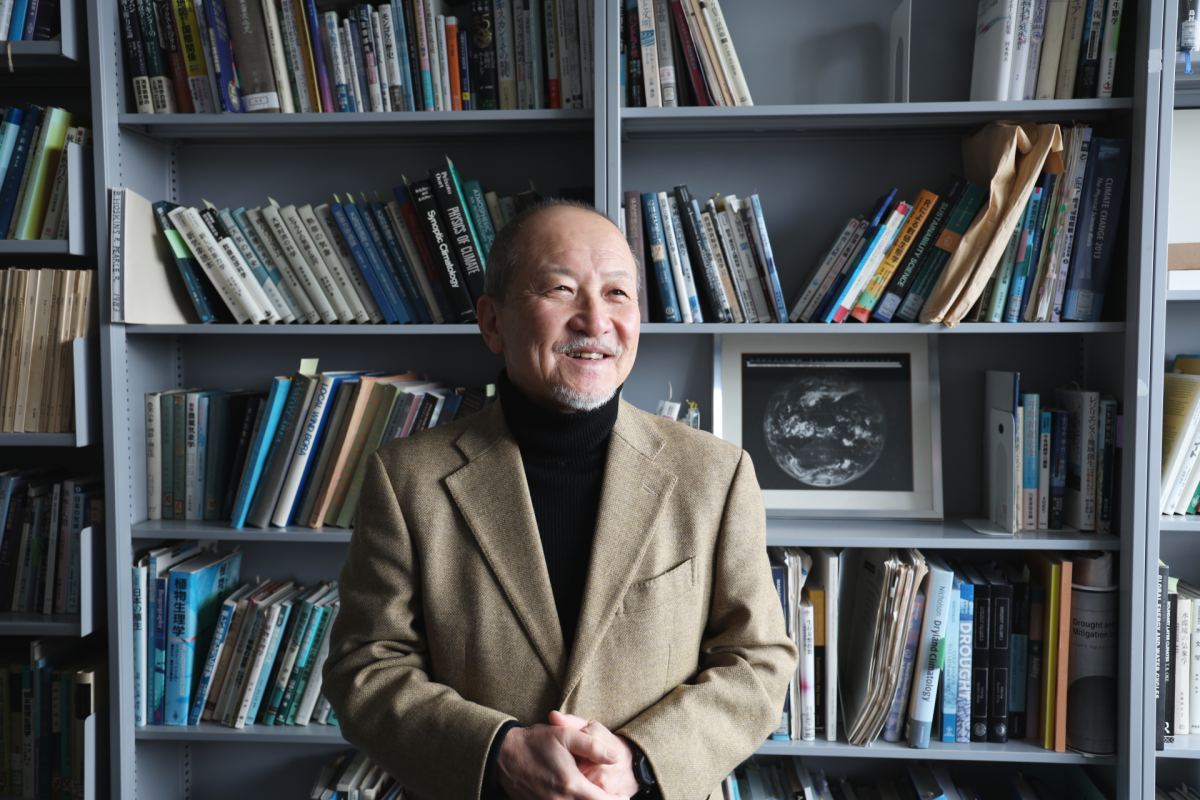この写真は春先のゴビ砂漠の風景であるが、ラクダが砂嵐のなかで難渋しながらも行進している様子がわかる。この場所は皆さんの生活と無関係ではない。そこからダスト(黄砂)が飛来して、空色を濁し、アレルギー症状をきたしているかもしれない。
写真は、表題の4Dプロジェクトのホームページに使ったもので、それに深く関わるダスト研究が行われた場所だ。4Dとは4次元のことではない。Dust(砂塵嵐)、Dzud(ゾドとよばれる寒雪害)、Drought(干ばつ)、Desertification(砂漠化)をまとめ、頭文字をとってそうよんでいる。これらは、ユーラシア乾燥地に特有な4種類の自然災害であり、このプロジェクトは、科研費「乾燥地災害学の体系化」(2013~2017年)の中で、4D災害を干ばつとそれから派生するものの災害群ととらえ、ひとつのリスク評価の枠組みのなかでとらえた。
世界の乾燥地は陸地の約4割を占め、そこに世界人口の3分の1の人々が暮らしている。その多くは途上国の貧困層であり、自然‐社会システムは脆弱ゆえに突発的な自然災害による被害は甚大となる。極端気象の多発時代において、社会の脆弱性ゆえに気象災害が甚大な乾燥地の人々に対して、われわれの学際グループは「乾燥地災害学の体系化」に取り組み、災害に対する能動的対応を提言した。
そこで、鍵となるのは「気候メモリ」という概念である。これによって、災害発生機構の統合的理解ができた。気候メモリとは「異常気象の影響が地表面状態・生態系・人間活動に及び保持されること」である。これまでの研究で、少雨が原因で発生する気候メモリ(干ばつメモリ)よって、4D災害発生機構が解明できた。
つまり、「夏の干ばつ(少雨)→植生が少ない→翌春にダスト発生が多い→風食(砂漠化)が発生」と一連の現象を明らかにして、この文脈で3つのD災害が波及的に発生していることがわかった。この波及現象を丹念にとらえていけば、次に起こる災害の予測も可能となる。さらに、干ばつによって牧草が少ない冬に、多雪や低温(ゾド)になると、家畜の大量死が発生するので、4つのDがつながったことになる。
モンゴル現地は東アジアでダストの発生頻度が最も多い地域である。現地調査には困難がともなうが、そこで得られたデータは世界でひとつしかない貴重なものだ。しかも、そのデータがこれまで10年以上も蓄積され、ダスト発生の年々変化を調べることができるようになった。ダスト観測をはじめ、気象観測、土壌・植生・家畜・牧民調査を組み合わせることによって、4D災害の統合的理解が可能となった。このためには、私が長い研究者人生でともに歩んできた、さまざまな専門分野の仲間が不可欠であったことはいうまでもない。